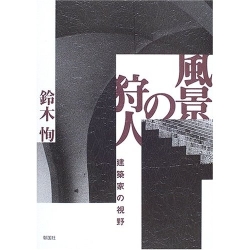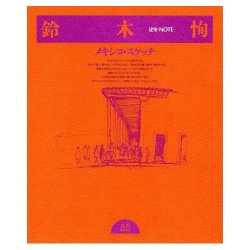『風景の狩人』。恩師、鈴木恂の論考を集めた書籍のタイトルである。鈴木は個人での渡航がまだ難しかった1960年代はじめから文字通り世界各地へと脚を伸ばし、スケッチや写真、論考といった形で思考の軌跡を重ねて来た。別の著書『光の街路』の冒頭に「遊歩の達人、吉阪隆正先生へ」と捧げられている通り、その師、吉阪隆正の遊歩に倣うかのように。
鈴木がある土地を訪ねる際、最も注意を注ぐのがその土地への「たどりつき方」とそこからの「去り方」だという。陸路か、空路か、その前に訪れる土地は、その後に訪れる土地は、ということを綿密に練り上げて来たようだ。旅を重ねる上で気持ちの高まりを演出するための彼ならではの方法ではないだろうか。
目的地となる街や村へ着いた後の行動を想像してみよう。おそらく彼はガイドブックの類いやマーキングした地図を手にしつつ、スタンプラリーに興じるようにいわゆる名所・名建築を巡る、という方法は取らない。あらかじめの知識に基づく体験、というものをあまり信用していないようなのだ。それよりも、生のまま街に出て、その土地や人々、その生活を鋭く観察する中で彼が次に観るべき場所を読み解いていく、というプロセスを重視しているようである。あらかじめの知識をもとにそれを確認しに行く作業は彼の旅の方法ではなく、而して彼の軌跡は至ってリニアなものになっているはずである。そのリニアで数珠つなぎともいえる狩りのエリアを徐々に広げ、面的なものに再構成しているように見受けられる。
鈴木がそうした方法に至るにあたっての紆余曲折については、別掲のインタビュー「実測とスケッチ/撮影」*に譲るが、彼が自身の方法論を決する上で大きな契機となったのは、メキシコをはじめとした中米への調査旅行だったといってよい。